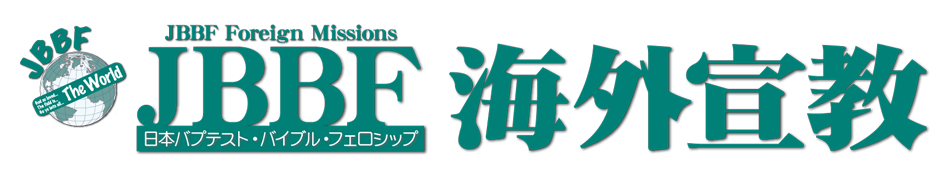過去の宣教メッセージ
次の旅に送り出す責務
平塚聖書バプテスト教会牧師 三谷 浩司

「愛する者よ。あなたが、旅をしているあの兄弟たちのために行なっているいろいろなことは、真実な行ないです。彼らは教会の集まりであなたの愛についてあかししました。あなたが神にふさわしいしかたで彼らを次の旅に送り出してくれるなら、それはりっぱなことです。彼らは御名のために出て行きました。異邦人からは何も受けていません。ですから、私たちはこのような人々をもてなすべきです。そうすれば、私たちは真理のために彼らの同労者となれるのです。」 第3ヨハネの手紙5〜8節
JBBFの宣教師は、概ね4年に一度「ファーロー」すなわち宣教報告および祈りと支援の要請のための諸教会訪問のために本国に帰国することが海外宣教規約で決められています。しかしファーローの目的はそれだけでなく、宣教師および宣教師家族の健康管理と休息という大切な目的があるのです。
宣教師の困難
海外宣教地での生活は、「宣教ハンドブック」にも掲載されているように、日本にいる私たちには分かりにくい多くの困難があります。
まず第一に、生活環境の違いです。宣教地の気候・食べ物・臭い・騒音等により、身体的にも精神的にも相当な負担がかかります。
インドネシアのように一年中暑い国や、反対にロシアのように冬は極寒になる国では、健康管理が非常に難しいです。食べ物の味付けの違いで美味しく食べられないとか、衛生面において安心して食べられないこともあります。発展途上国では生ごみや汚物が散乱して、ひどい臭気が漂っている地域もあります。イスラム教国ではモスクから「コーラン」の朗読がスピーカーから大音量で流れてきます。私たちはそうした地域に旅行で数日間滞在しただけで、うんざりしてしまうものですが、宣教師は何年もそこに留まって生活し続けなければならないのです。
第二に、言葉や思考や常識の違いです。現地の人と意思疎通が取りにくいことや、日本では考えられない慣習や良識の大きな差はかなりのストレスになります。
たとえば、日本人は時間に割と正確ですが、ウガンダのように時間にルーズなところもあります。「ボランボラン(急がないでゆっくり)」と言って、礼拝開始時間になってもほとんど人が集って来ず、30分以上遅れて礼拝が始まることなど日常茶飯事だそうです。きっと私の性格だったらイライラして我慢できないと思います。
また以前インドネシアの入江宣教師から、教会の備品を信徒が勝手に持ち帰ることが良くあると聞きました。それは、持てる者は持たざる者に分け与えるのは当然だという考え方があるからだそうです。
第三に、経済的な問題です。宣教師は現地でアルバイトすることはできないため、すべて諸教会からのサポートに拠り頼んでいます。まさに「異邦人からは何も受けていません」です。
しかし毎月のようにサポート額の増減や為替の変動があるため、経済管理が非常に大変です。この2年間で20%以上円安になりましたが、サラリーマン的に考えると20%の減収は死活問題です。それに医療制度の違い、食料品や生活必需品の外国人価格などで、思わぬ出費を強いられることもあります。
実際、かつての円高の時に経済的な問題で日本から本国に戻ったアメリカ人宣教師もいたと聞きます。
第四に、子弟の教育の問題です。宣教地ではよほどの大都市でないと日本人学校がないケースが多く、もしあったとしても学費がとても高いです。ホームスクールという方法もありますが、おもに勉強を教える立場になる宣教師夫人は、そのために週日は毎日数時間を消費する上に家事と宣教の働きもあるため、その負担の大きさは計り知れません。
宣教師およびその家族は、そうした多くの様々な身体的・精神的な負担による疲れや経済的な不安を抱えつつファーローのために一時帰国していることを、受け入れる教会は良く理解しなければなりません。
ガイオのもてなし
そしてガイオのように、キリストの御名のために出て行った宣教師たちを「神にふさわしいしかた」で次の宣教の旅に送り出さなければなりません。
当時の宣教師(あるいは巡回伝道者)は、パウロが「幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、海上の難、にせ兄弟の難に会い、労し苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。」(第二コリント11:26-27)と証しているように、非常に困難な中で宣教の働きをしていました。ガイオはそのような宣教師たちの労苦を良く知っていたので、「いろいろなこと」を行なって彼らをもてなしたのです。
それがどのようなもてなしかは記されていませんが、きっと、彼らのために美味しくて栄養価があり体に良い食事を用意したり、ぐっすり眠れるように細やかな宿泊の配慮をしたり、気分転換できるような楽しいイベントに連れて行ったり、時には彼らの抱えている悩みや苦しみをじっくり聞いて重荷を少しでも軽くさせたりしたことでしょう。そうしたガイオの愛のこもったもてなしは、その兄弟たちが他の教会の集まりであかしせずにはいられないほどの、忘れがたく感謝に満ちあふれるものでした。おそらく彼は、自分も宣教地にいるような気持ちで彼らを思いやり(ヘブル13:3)、キリストの愛と真実をもって誠心誠意もてなしたに違いありません。
宣教師も私たちと同じ弱さをもった人間ですから、身体的・精神的な疲れや経済的な心配から、「もう宣教地に戻りたくない」とファーロー中に思う時もあるでしょう。
しかし、そんな状態のまま宣教地に旅立つならば、疲れ果ててリタイアする危険性が高くなります。ですからファーローを受け入れる教会は、ガイオがしたように宣教師が身体的にも精神的に十分な休息を取って霊的な力を充足できるように愛と思いやりをもってもてなし、また経済的な不安を抱えずに次の宣教の旅に出られるように必要を満たすことにより(テトス3:13)、ファーローに来訪した宣教師が「よし、また宣教地に行くぞ!」と思うことができるように力づけ、励ます責任と義務があるのです。
そして、その責務を果たすことにより、私たちは真理であるキリストの福音を宣べ伝えるために全世界に出て行く宣教師たちの「同労者」すなわち「ともに行って働く者」となる恵みにあずかることができるのです。
祭司の王国
すずらん聖書バプテスト教会牧師 エバンズ・トニー
 「あなたがたはわたしにとって祭司の王国、聖なる国民となる。これが、イスラエル人にあなたの語るべきことばである。」出エジプト記19:5-6
「あなたがたはわたしにとって祭司の王国、聖なる国民となる。これが、イスラエル人にあなたの語るべきことばである。」出エジプト記19:5-6
シナイ山で与えられたみことば
こ のみことばが与えられた時、イスラエルはシナイ山に到着していて、400年途切れていた神との関係が改められようとしていました。彼らはアブラハム、イサ ク、ヤコブを通して特別な契約をいただいていたわけではありますが、400年のエジプトでの生活によって、それに対する意識が薄くなっていました。天の神 よりもエジプトの偶像を日々見ていたでしょうから、彼らの『信仰』は、どれだけこの世に染まっていたことでしょう。
出エジプトであらわされた神の力
エジプトを出る前に、彼らの信仰が大きく試されました。モーセとパロとの間のやり取りが続く中で、天の神に対する信仰と大きな疑問が交互に続く状態でした。各災害がくることによって、エジプトの神々の無力さがはっきりと証明されました。
最後に、過ぎ越しの時、モーセを通して語られた神の言葉に従うことによって、天の神に対する信仰が徹底されました。子羊の血、そこだけに救いがあったのです。
他にも奇跡的なエジプトからの解放、紅海の横断、エジプト軍の全滅、シナイ山までの様々な試練もありました。
一つ一つを通して、神の愛、忠実や全能がはっきりと見せられました。
そして今、契約によって神は彼らの生き方を整えるだけでなく、一つの使命を与えようとされています。
イスラエルに与えられた使命
その使命とは?
祭司の王国になること、聖なる民となることでした。十戒を始め、与えられた律法は彼らに聖さを定義するものでした。神様の心、罪、贖い、和解、その他に多くの大事な概念が示されました。
「祭司の王国」の意味とは
しかし、祭司の王国とはどういう意味でしょうか。祭司とは、人と神の間の仲介の役を果たす人のことです。祭司職に任命されたアロンを含むレビ族は、他の十一部族と神との間の仲介を務めました。
同じように祭司の王国とは、全イスラエル人が祭司役を務めることによって、神のことが他の国民に伝えられる、という意味ではないでしょうか。
この使命を果たすために、まず彼らは自分を聖く保ちながら、自分の置かれた場所で、神に与えられた仕事を成し遂げるべきでした。すなわち、彼らの目の前にあるカナンの地に入り、そこの土地を征服し、そして初めて神の素晴らしさを伝え始めることができたでしょう。
しかし彼らは失敗してしまいます。完全な征服もできず、聖さも保てず、結局は自分と神様との間の関係が十分に構築できませんでした。基礎の部分で失敗したのですから、祭司の王国の役目が彼らの意識から消えたのも驚くようなことではありません。結果として彼らは自分たちの周りにいる敵に圧倒され、国内の一致や敵からくる攻撃に対処することだけが存在の目的になってしまい、外の必要に対する働きかけがほとんどできませんでした。
ダビデは詩篇で祭司の王国としての務めを謳っていた
しかし詩篇を見ると、イスラエルに与えられていたこの使命に関する様々なことをダビデはよく理解していたことがわかります。
①地獄の恐ろしさを。「悪者どもは、よみに帰って行く。神を忘れたあらゆる国々も。」(詩編9:17)
②自分たちが得ている祝福によって、他の国々が神の救いを知るべきことを。「どうか、神が私たちをあわれみ、祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かしてくださるように。セラ それは、あなたの道が地の上に、あなたの御救いがすべての国々の間に知られるためです。」(詩編67:1-2)
③神のご計画はイスラエルだけでなく、すべての国々まで至るものだと。 「 彼の名はとこしえに続き、その名は日の照るかぎり、いや増し、人々は彼によって祝福され、すべての国々は彼をほめたたえますように。」(詩編72:17)
残念なことに、ダビデの信仰とビジョンが後の世代に引き継がれることはなく、祭司の王国の働きは果たされませんでした。
エゼキエル書を読むと、「彼ら(もしくはおまえたち)は、わたしが主であることを知ろう。」のようなことばが70回以上繰り返されます。
神の切なる願いとは
神の切なる願いは、ご自分が神として知られ、神として崇められることでしたが、イスラエルはそのことに対する意識も失い、それに伴う使命も失っていました。
ですから何も驚くことではないのです。神様が、古い皮袋であるイスラエルに、新しいぶどう酒であるご聖霊を入れようとしなかったことは―(マタイ9:17)
また、神が異なった舌により、信じないイスラエルに語り、また裁かれたことは―(Iコリント14:21-22)
さらに、イスラエルに与えられた祭司の王国の責任が、今度は教会に移されたことは―(Iペテロ2:9)
この終わりの日にこそ、私たちはイスラエルの失敗から学び、自分に与えられた使命を果たそうではありませんか!
祭司の務めを自分の存在の意義として力強く握り、私たちにとってのエルサレムとユダヤ(日本)から始まり、サマリヤ(アジア)や地の果てにまで、福音の光を明るく輝かせようではありませんか!
働き手を送っていただく祈り
横浜聖書バプテスト教会宣教牧師 山宮 利忠
 「そのとき弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから、収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。」 マタイ9章36〜38節
「そのとき弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから、収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。」 マタイ9章36〜38節
「あなたがたは、「刈り入れ時が来るまでに、未だ四か月ある」と言ってはいませんか。さあ、わたしの言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっています」 ヨハネ4章35節
交わりのある諸教会が、世代の交代の時期を迎え、確かに働き手としての伝道者の少なさを痛感させられている時であり、各地で「働き手を送ってください」という声を聞く事が多くなりました。海外に遣わされた宣教師からも、「もっと多くの宣教師を送り出してください。」という願いや、現地の教会の牧会を委ねる牧師の必要があって、その養成のためにご苦労されている現状をお聞きします。
今後、ますます福音宣教の為、主のお体なる教会の養いの為に仕える牧会者としての働き手の必要が増すことになるでしょう。
主は、ここに働き手が少ないと言う事と、畑は既に刈り入れる時が来ているという、二つの重要な点を指摘しておいでです。
第一に、畑は既に色づいて刈り入れるばかりになっている。
働き手を送り出していただく為に、「収穫は多い」と言う主のおことばに、しっかり耳を傾ける必要があります。
確かに、巷を見れば数え切れない群集が滅びに向かって突進している姿を目にし、それとは逆に救われる魂の少なさが目立ちます。しかし、畑は既に色づいて刈り入れるばかりになっていると言う認識が、私にあったかと言うとそうではありませんでした。
実を結ばない現状に、疲れ果て、収穫の少なさに落胆が先立ち、収穫の少なさに多くの理由をつけては自らを納得させようとする自分がありました。
主の御目からご覧になれば、魂は、救いの必要が既に満ちて色づき、救いを待っている多くの魂があることになります。
パウロは、堕落の町コリントにおいて、その伝道の困難さの故に「弱く、おそれおののいていた」(1コリント2:3)時、主は、「恐れないで、語り続けなさい。黙っていてはいけない。わたしがあなたとともにいるのだ。だれもあなたを襲って、危害を加える者はない。この町には、私の民がたくさんいるから。」(使徒18:9)と励まされました。主の約束の中に「この町には、わたしの民が多くいる。」と言うお言葉はなんと大きな励ましになるお言葉でしょうか。私の見る目では、救われるものが少なく、事実、救われるものは、少ないのです。しかし、刈り取らない魂が多くあると、主はおっしゃるのです。
収穫の主から見れば、刈り取られない穂は、やがて腐って役立たないばかりか、害になり、漁る魚が沢山いながら取り入れない魚が沢山あれば、なんと主のみ心を痛めることでしょう。
実を結ばない現状に、疲れ果て、収穫の少なさに落胆が先立ち、収穫の少なさに多くの理由をつけては自らを納得させようとする自分がありました。主の御目からご覧になれば、魂は、救いの必要が既に満ちて色づき、救いを待っている多くの魂があることになります。・・・願わくは、主のお声を聞いて、収穫の畑に遣わされる者が多く、召し出され、主の御心に従う方が起こされますように。
私は、静岡県の清水で子供の頃過ごしました。清水港は貿易港であると共に、漁港でもあり、私の近所には漁師の方が多く、威勢の良い声が毎晩のように聞こえてきたものです。特に漁の多い大漁の時には、その威勢は、際立って大きいものでした。しかし,漁がない時の彼らは、一声も発することなく、真に静かなもので、「ああ、今日は、漁がなかったのだな。」と、すぐに判ったものです。天候にも左右され、漁の場所にも左右されるのでしょう。しかし、漁がなければ、彼らの死活問題なのです。なんとしても魚をとらなければなりません。
人を漁どる漁師とされた伝道者が、漁をする事をもって喜びとし又、生きる糧を得る事が出来ます。刈り入れるばかりになっている畑、多くの魚が群れている海、そこに必要なのは、この主のおことばでありましょう。未だ早い、ここは魚がいない、少ない、難しいと言えば、主のおことばに反する事になります。
私は、畑が色ずいていることは感じていても、収穫は、多いという強い確信をもって主に御仕えしてきたかと問われると、真に怪しいものです。私の目には収穫は少ないと見えても、主の御目には多いのです。収穫の多さを信じて働くことこそが、御心にかなった働き方なのでしょう。
第二に、働き人が少ないのです。
主の働きと、魂の刈り入れのための働くにつく人が少ないと、主は仰います。収穫は多く、刈り入れるものも多いのに刈り取る仕事をする人がいないということは、大問題です。
私は、これまでの牧会で、働き人を送ってくださいと真剣に祈ってきただろうかと振り返ってみると、そうではなかったなと、反省せざるをえません。
もちろん献身者の召しは人が与える事の出来ないものです。さらに、献身者の指導は、多くの時間と手間と犠牲が必要となります。いきおい、真剣に働き人を送ってください、私の教会から働き人を起こしてください、と祈ることが消極的になります。
主が働き人を起こしてくださるのであれば、主がお守りくださると信じる事こそが、私のあるべきあり方なのでしょう。主が責任を持ってくださると信じる事は知っていてもなかなか出来なかったのが現実でした。伝道者の働きの困難さを知れば知るほど、働き人を送って下さいと祈ることが難しくなったと言うわけです。
涙を流して出て行く、泣きながら束を抱えて出て行くことばかりに心を捉えられて、喜び、叫びながら帰ってくることへの強い思いと信仰が必要でした。また、喜び叫びながら帰ってくる働き人の姿と模範を多く見てこなかったことも、その原因の一つかもしれません。
「涙と共に種を蒔く者は、喜び叫びながら刈り取ろう。種入れかかえ、泣きながら出て行く者は、束をかかえ,喜び叫びながら帰ってくる。」(詩篇126:5)
第三に、祈ることです。
魂を主の御元にお導きする事のために、私達のできることは、まず、祈ることだと主は仰います。遣わしてください、と祈ることの中に、私の教会から誰かをと言う事だけではなく、わたくしも刈り入れの畑に遣わしてくださいと、祈る聖徒が一人でも多く必要ではありませんか。もしあなたが、主のおことばを受けて、多くの刈り入れが待っている、はや色づいて刈り入れるばかりだと言う事を信じる事ができれば、真剣に祈らねばなりません。誰かではなく私も刈り入れの畑に遣わしてください、と祈る必要があります。
「私は、だれを遣わそう。だれが、われわれのために行くだろう。と言っておられる主の声を聞いたので、言った。ここに私がおります。私を遣わしてください。」(イザヤ書6:8)
願わくは、主のお声を聞いて、収穫の畑に遣わされる者が多く、召し出され、主の御心に従う方が起こされますように。
太田聖書バプテスト教会牧師 能 吉雄
 1. 私が初めて「海外宣教」について知り学んだのは神学生の3年の時で、一年早く卒業された丸山一郎師が教鞭をとって下さいました。主の大命令はすべての教会・すべての教役者・すべての信徒に対するもので、教会の大小に係わらず、その義務・責任・命令から逃れる事が出来ない事を知らされました。今考えると、神学校における海外宣教教育がどんなに大切か、しみじみと感じさせられます。
1. 私が初めて「海外宣教」について知り学んだのは神学生の3年の時で、一年早く卒業された丸山一郎師が教鞭をとって下さいました。主の大命令はすべての教会・すべての教役者・すべての信徒に対するもので、教会の大小に係わらず、その義務・責任・命令から逃れる事が出来ない事を知らされました。今考えると、神学校における海外宣教教育がどんなに大切か、しみじみと感じさせられます。
2. その頃は、数名のアメリカからの宣教師が熱心に活動しておられましたが、なぜ宣教師が日本におられ、どのような動機で、どのような目的で活動しておられるのか、またその支援体制がどうなっているのか全くと言ってよいほど知りませんでした。ましてや、この群れには海外宣教委員会もなければ、日本人の宣教師もおられず、自分とどんな関わりがあるのかもつかめておりませんでした。「海外宣教」がどんな意味があるのかを悟るにはまだまだ時間と訓練が必要でした。
3. この未知な海外宣教に対して理解が余りにも不十分であっても、海外宣教が主によって与えられた生涯の自分の責任として捉える事が出来たのは、自分の「信仰の質の変化」が大きな要因であったと思っております。信徒時代から神学校に入学して一年の夏休みまでの間、私はローマ7:14-24、特に「善をしようとする意志は、自分にあるが、それをする力がないからである」・「私はなんというみじめな人間なのだろう。だれが、この死の体から、私を救ってくれるだろうか」との自覚に苦しんでおりました。と言うのも、イエス様がマルコ7:20-23「人の心から悪しき思いが出てくる…」と言われた罪の自覚は小学生の時からあり、神学校に入ってからはますます罪の自覚が増し加わり、ひたすら十字架の主を仰ぎ見るばかりでした。「おお主よ!お赦しください。もう一度、頑張ります」の連続。「信仰とは苦しむものなり」。当時の母教会の牧師に告げた心の内でした。個々の罪が問題なのではない。私自身がいけないのだ。しかし、この問題に対して根本的な解決の時がやってきました。Ⅱコリント4:10~11に触れた時、大きなショックを受けました。これらの罪に対してどうしようもない私であるからこそ、栄光の主は私の心の中に宿り、私の新しい命となっておられるのだと悟らされた事です。栄光の主の命は私の命そのもの。その時から「私が頑張ります」と自分の力で何かをやるのではなく、「やらせて頂く」と言う自覚に変化しました。もはや自分の無力さ・愚かさに悩むのではなく、こんな私だからこそ、栄光の主は私の内側に宿って下さるのだという大きく意識の変化がありました。この時から「信仰とは喜び・やすらぎ・恵みなり」となったのです。その結果、主の権威は自然な形で私の中に形つくられてきました。個々の罪の自覚しかなかった頃とは比較のしようがないくらい、主への信頼は深められていきました。この観点から私の海外宣教を見つめなおしてみると、主の大命令は、私の理解の深さや体験と関係なく、当然な主のみ心として私の内に定着しておりました。
主の大命令にあるように目を外に、特に海外宣教に向けるようにしましょう!そこにおのずから「終末の時代」にもかかわらず活力に満ちる教会の残される道が開かれていくと確信します。
4. 海外宣教が主により私に課せられた生涯の私の使命としてゆるぎなく自覚された事の次の大きな要素は、副牧師時代の10年間の個人伝道・訪問伝道の徹底的な訓練を受けた事でした。魂を捕らえた時の喜び・感動は「水汲みし僕は知れり」でした。この魂の収穫の喜びと共に苦しさ・辛さ・悲しさ・困難さ・辱め・孤独感を数知れず体験した事でした。この体験が国内開拓ばかりか宣教師の異国での苦労の如何ばかりかを肌で感じ取るものとなりました。
5. 太田教会の会堂には私が牧師として就任して以来、掲げておりますスローガンがあります。「私達の教会の最高の働きは世界の宣教である」。これはカナダ・トロントの故オスワルド・スミス師の言葉です。主の大命令の精神を的確に表現しているものとして、私の生涯の座右の銘として受け入れると共に、牧会の基本姿勢としております。このスローガンを掲げるに当たり、海外宣教に関わる一つの大切な決断を経験しました。主の大命令に応答するために、私は具体的にどうすべきなのかという点でした。すべての教会・すべての信徒は、誰しもこの大命令と向き合わなければならないのだけれど、私はどうすべきなのだろうかと問われた事です。この大命令に対して二種類の応答があります。一つは、私自身が宣教師として出て行くという点で、この事は長い間の祈りの課題でした。そして得た答えは国内に留まる事でした。その代わり私が国内に留まるのは、自分の好みに関係なく海外で労する宣教師を経済的にも霊的にも支援する事でした。その働きを誠実に取り組む教会を養い育て、かつ私に替わって出て行く宣教師を育てる事。これが国内に留まる私の責務であると確信しました。この決断がスローガンを掲げた理由です。それ故、就任して間もない頃、開拓伝道以上に困難な状況の中にあって教会会計が赤字になった時に牧師給を削っても宣教師への約束献金を護り続ける事の出来た理由でした。後程、教会会計が満たされるようになってから補填させてもらいましたが。その重荷の延長線上に娘の献身がありました。
6. 最後に取り組んだのが、教会として宣教師の働きに対する「執成しの祈り」を継続させる事でした。当初、諸集会の中の数々の祈りの中に、宣教師の事も加えさせて頂いておりましたが、宣教師の数が増し加わるに従い、それが困難である事に気がつきました。JBBFの海外宣教委員会に出席したおり、祈りのグループを作る事の大切さを知らされ、教会内において「MPBの時間」を設ける事にしました。毎月第4主の日の午後の礼拝を海外宣教の祝福を求める時としました。幸いにも教会内に宣教委員会がありましたので、委員達が協力分担して毎月の宣教師からの報告を整理し、祈りの表としてまとめ、口頭による補則説明を加えながら、宣教師の現状をなるべく詳しく理解出来るように心を尽してくれました。その忠実な労苦により、教会としての海外の情熱を育て、継続させると共に、信徒たちはその報告の裏に秘められた苦しみや問題点にも思いを馳せるようになりました。この祈りの形が出来てから早や20年以上になりますが、今も教会としての海外宣教への情熱の原動力となっております。
7. これらの事柄を顧みて、海外宣教がキリスト教界全体でいよいよ盛んとなるためには、自分の神体験が如何なる深みのものであるかをもう一度考え、栄光の主が自分の命であることを一人一人が自覚する事ではないでしょうか。ガラテヤ2:19,20は、私の体験・証しだと自覚する処から主のみ心へのゆるぎない服従と忠誠が養われていくのではないでしょうか。そして教会の中に個人伝道・訪問伝道の何であるかを体験しなおす処から、海外宣教への情熱は新たにされてくるのではないでしょうか。これらは教会の若返りと成長・信仰の伝承そのものへと波及していくと確信しております。
諸教会の皆さま!これからの祖国は、様々な混乱の時代へと巻き込まれていくと思われます。北朝イスラエルのように偶像崇拝がますます盛んになり、福音宣教の困難は度を増していく事が予測されます。だからこそ明確な聖書信仰を確立し、個々の教会・信徒が「私は自分の救い主を知っている」と告白し、主の大命令にあるように目を外に、特に海外宣教に向けるようにしましょう!そこにおのずから「終末の時代」にもかかわらず活力に満ちる教会の残される道が開かれていくと確信します。