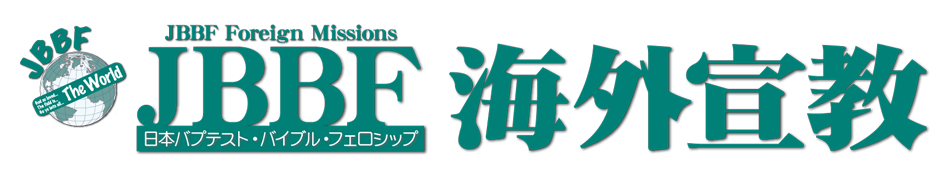過去の宣教メッセージ
神は全ての人の救いを待っておられる

港北ニュータウン聖書バプテスト教会牧師 鹿毛独歩
「すると、再び声があって、彼にこう言った。『神がきよめた物を、きよくないと言ってはならない。』」使徒の働き10章15節
聖霊行伝
「使徒の働き」は、初代教会の宣教の歴史です。主イエスの昇天の後、聖霊がこの世界に降られ、全世界への福音宣教の力となられた歴史でもあります。それゆえに「聖霊行伝」とも言われたのです。聖霊なる神は、五旬節(ペンテコステ)の日、それまで恐れおののいていた弟子たちに降られました。その多くはガリラヤの田舎の出身でありました。その日、弟子たちは習ったこともない外国の言葉で、キリストの福音を証しし始めたのです。それは突然の大事件でした。人々はこの不思議な出来事に驚き「いったいこれはどうしたことか」と互いに話し合ったのです。
キリスト教信仰による魂の救いは、人の理性では計り知ることができない大きな驚くべき出来事です。人の心、生活、生き方、価値観さえも変えてしまう出来事だからです。それまで自分中心で常に損得勘定で行動していた人が、キリストを信じた時から、ただ神の愛によって生きることを選択するようになるのです。私たちは、ここに聖霊の豊かな働きを見るのです。しかし、多くの人々は「一時的な感情に酔っているのだ」「洗脳され、騙されているのだ」「それこそ損な生き方ではないか」と批判します。
神は、キリストによって人が最も必要としている「罪の赦し」と「永遠のいのち」の祝福を約束してくださいました。これこそ、神が全人類に与えられた最高の賜物(贈り物)です。しかし、人の心はかたくなで、聖書のみことばを知ろうとも、受け入れようともしません。そして、むなしい偶像に対しては、伝統、習俗として何のためらいもなく膝をかがめるのです。聖霊は、このような様々な文化の中から、キリストの教会をお立てになりました。教会は、キリストの福音を宣べ伝える神の福音の砦です。
教会は、このすばらしいキリストの福音を伝え続ける使命があります。しかし、時々、目の前の働きの忙しさの中で、神の命令と神のみこころを忘れてしまうことがあるのではないでしょうか。それは、神の救いの福音は、全世界の人々に提供されているということ、また、福音宣教の大命令は全世界に出て行くことが求められているということです。
ペテロへの幻は、彼らユダヤ人たちが持っていた古い律法的な価値観を打ち破る神のチャレンジでした。ペテロは幻の中で、これまで律法の中で「きよくない動物、汚れているとされた動物」が敷布に包まれ、天から降りてくるのを見たのです。そして、天から「ペテロ、さあ、ほふって食べなさい。」との声がしました。彼は「主よ。それはできません。私は、まだ一度も、きよくない物や汚れた物を食べたことがありません。」それは旧約聖書の神の定めだったからです。しかし、神は言われました。「神がきよめた物を、きよくないと言ってはならない。」
神のみこころが変わったのでしょうか。神のみこころは決して変わってはいないのです。神はアブラハムに天の星を見上げさせ「あなたの子孫はこのようになる。」と語られました。また、預言者ヨナを敵国ニネベに遣わし、「わたしはこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか、そこには、右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜がいるではないか。」と仰せられたのです。南ユダ王国を滅ぼしたバビロニアにおいてもダニエルを通して、神はご自身の栄光を現されました。神はすべての創造主であり、すべての造られた者を愛し、あわれんでおられるのです。
神の御子イエス・キリストによって神の救いのみわざは完成しました。そして、神は、イスラエルを通して、全世界にキリストの救いを明らかにされたのです。ハドソン・テーラーが中国の奥地に宣教をした時、救われた中国人は彼に尋ねました。「この福音が、イギリスに伝えられてから何年になるのですか。」ハドソン・テーラーは「数百年前になります。」と答えると、彼は言いました。「何ということです。この福音を数百年も前に知っていながら、今やっと伝えに来るなんて。私の父は20年以上も真理を求めていました。そして、見出せずに死にました。ああ、なぜ、もっと早く来て下さらなかったのです。」
国際社会の中で大きな経済力を持つ日本は、世界各地にビジネスマンを送り出し、メイド・イン・ジャパンの製品を世界へと輸出しています。しかし、「どれほど福音のために、人を送り出し、犠牲を払っていますか。」と問われるならば、私たちの手の中には、乏しいささげ物しかないのです。ペテロは、神のおことばを聞きながらも「主よ。それはできません。」と神の命令を拒みました。私たちも、その働きの乏しいことの理由をいくつも挙げることはできるでしょう。「教会がまだ小さいですから」「日本にはまだ救われていない人が多くいますから」「働き人がいませんから」。この幻が三回も繰り返し繰り返し示された時、ペテロは神がこの福音を異邦人にも宣べ伝えることを良しとされていることを知ったのです。
聖霊は、私たちに信仰の気づきを与えてくださいます。キリストの福音の宣教は、神の最大の願いであるということです。神はすべての滅び行く民をあわれみ、全世界への福音宣教の時、恵みの時を今もなお延ばしておられるということです。
考えてみるならば、日本の宣教も、世界宣教の大きなビジョンによって祈られ、遣わされた宣教師たちによって福音の種が撒かれてきたはずです。神は世界宣教の働きの中で、私たちを召し出し、それぞれのところに遣わしておられるのです。それが海外であるか、日本国内であるかという違いがあるだけです。神にとって、その一人の魂の重さは同じです。
救いを求める魂の叫びを聞きながら、共に祈り、まだ福音を知らずに滅びに向かう魂の救いのために仕える者となりましょう。
数年前、台湾に行かせていただいた時、台湾人の牧師夫人が「私の親は日本語世代であり、自分の親でありながら、日本語で福音を伝えることができません。日本から福音の働き人を送ってください。」その叫びは、今も私の心に響いているのです。
真のフルタイム献身を目指して
岡崎聖書バプテスト教会牧師 疋田 健次

「ですから、兄弟たち、私は神のあわれみによって、あなたがたに勧めます。あなたがたのからだを、神に喜ばれる、聖なる生きたささげ物として献げなさい。それこそ、あなたがたにふさわしい礼拝です。」ローマ12:1
青年キャンプでの出来事
高校生のころからだったでしょうか。毎年5月に行われる青年フェロシップキャンプに参加するようになりました。キャンプに行くと、同じ世代のクリスチャンに会うことができます。それは私にとって、とても楽しいひと時でした。しかし、そんな楽しいキャンプのなかで、唯一、苦手な時間がありました。メッセージの後の招きの時間です。毎年毎年、講師の先生方は、決まってこのように言われます。「主のためにフルタイム献身の決心をする人はいませんか?」。
「フルタイム献身…」。この言葉は当時の私にとって、とても恐ろしい言葉でした。キャンプに参加する度に、この言葉が私の背中に重くのしかかってくるようでした。なぜなら私は、「牧師には、なりたくない!」と考えていたからです。そのような私が今、牧師として主と教会にお仕えさせていただいていることは、本当に不思議なことです。主のお取り扱いとしか言うことができません。
フルタイム献身への誤解
「フルタイム献身」という言葉は、牧師や宣教師などといった直接的に宣教の働きに携わる仕事に就くこと。あるいは、その道に進むこと…といった意味合いで用いられているかと思います。「フルタイム」という言葉を辞書で引くと、「全時間」「常時」「決まった勤務時間の全時間帯を働くこと」「常勤」と出てきます。ですから、職業(プロフェッショナル)として宣教の働きに携わること=フルタイム献身と呼ぶのは、正しいと言えるでしょう。
しかし、この言葉は、ある面において、誤解を生み出すことがあるのではないかと考えています。いや、私自身がまさに、長い間、誤解していた言葉なのです。
ここにありました。「牧師や宣教師になることがフルタイム献身ならば、それ以外の道に進むことはパートタイム献身なのだろう」。私はそのように考えていたのです。
「日曜日は教会に行って礼拝しているし、献金もしている。トラクト配布をすることもある。でも、他の日まで奉仕をすることはできない。私はフルタイム献身者ではないのだから」。さらに私は、次のように考えるようになっていきました。「伝道は牧師や宣教師がするもの。私の役割はサポートであって、直接的な働きは関係ない。私はフルタイム献身者ではないのだから」。私はフルタイム献身者ではないことを言い訳にして、自分自身を宣教の働きから遠ざけようとしていたのだと思います。しかしある時、この考えが間違っていることに気づかされたのです。
献身は誰に命じられているのか
そもそも聖書は、献身を「フルタイム」「パートタイム」というふうに分けているのでしょうか。あるいは、特別な人たちにだけ献身するよう命じているのでしょうか。ローマ12章1節には、このように書かれています。
「ですから、兄弟たち、私は神のあわれみによって、あなたがたに勧めます。あなたがたのからだを、神に喜ばれる、聖なる生きたささげ物として献げなさい。それこそ、あなたがたにふさわしい礼拝です」
これはまさに献身について教えている御言葉です。問題は、この御言葉が誰に向けて語られているかです。パウロは「兄弟たち!」と呼びかけています。牧師や監督、長老たちに呼びかけているのではありません。つまりパウロは、すべてのクリスチャンに対して、献身することを勧めているのです。
私自身も便宜上、フルタイム献身という言葉を使うことがあります。また、牧師や宣教師の道に進む人には、ある面において特別な献身が求められているということも事実でしょう。しかし、クリスチャンであるならば、たとえどのような道を歩むにしても、フルタイムの献身者であるべきだと聖書は教えているのではないでしょうか。
Ⅰコリント10章31節には、次のように書かれています。「こういうわけで、あなたがたは、食べるにも飲むにも、何をするにも、すべて神の栄光を現すためにしなさい」
真のフルタイム献身とは、その人が自分自身の人生のすべてをとおして、それこそ「食べること」や「飲むこと」などといった日常生活のほんの小さなことをとおしてさえ、主なる神様のご栄光をあらわしていくことなのだと思います。
全てのクリスチャンは伝道者として立てられている
昨年、発行された宣教クォータリーのなかで、信徒による宣教についてのメッセージが掲載されていました。使徒行伝のなかには、パウロやペテロといった使徒たちの宣教の働きが記されているだけでなく、普通の信徒たちによって町々に福音が宣べ伝えられていったことも記されている。そうした信徒たちの働きが各地の教会の基礎となっていった…と書かれていました。
これは、初代教会の時代だけの特別な出来事だったのでしょうか。現代の教会には当てはまらないのでしょうか。そうではありません。昔も今も、すべてのクリスチャンは、よみがえられたキリストの証し人であり、それぞれの場所において立てられた伝道者なのです。かつての私のような誤解があってはなりません。「伝道は牧師や宣教師だけの特別な働きで、自分とは関係ない」という誤解です。
私たちの人生は一人ひとり異なります。ある人は教師として、ある人は看護士として、ある人は大工として、ある人は営業マンとして、ある人は芸術家として…。他にもさまざまな職業や人生があるでしょう。これからどんな仕事に就こうかと考えている学生たちもいます。そのなかには将来、牧師や宣教師の道に進む人がいるのかもしれません(若い青年の皆さんはぜひ、このことについて真剣に祈ってください)。しかし、たとえどの道に進むにしても、私たちは皆、献身者であり、伝道者であることを覚えたいと思います。
教会の一人ひとりが、それぞれ立てられているところで、真のフルタイム献身者として歩んでいくとき、福音宣教の力はより豊かなものとなっていくのではないでしょうか。宣教とは、トラクトを配ること、訪問伝道や個人伝道をすること、伝道集会を行うことだけではありません。食べること、飲むことさえも、実は宣教につながっているのだと思います。究極的には、私たちの人生そのものが福音宣教のためにあると言えるでしょう。
なぜなら、私たちが救いに召されたのは、神様のご栄光をあらわすために生きる者となるためだからです。このことを覚え、教会全体が一丸となって、福音宣教の働きに与っていくことができれば幸いです。
I Have No Man
小倉聖書バプテスト教会牧師 ケネス・ボード

「主よ。私には、水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけると、もうほかの人が先に降りて行くのです。」ヨハネの福音書5章7節
キリストは、38年もの間病気にかかっている人に会いました。キリストは彼に聞きました。「よくなりたいか。」7節に書いてあるその人の返事はとても悲しい返事です。「池の中に私を入れてくれる人がいません。」もし私は聖書に書いてある最も悲しい言葉のリストを作ったら、私はその病人の言葉をそのリストに入れます。「私を入れてくれる人がいません。」
英語の聖書に「I have no man.」と書いてあります。この箇所を読むたびに、私は聞きたくなります。「彼の親はどこですか。もう死んでいるでしょうか。」あるいは、「彼の兄弟はどこですか。いなかったでしょうか。」また、「彼を助けてくれる友達は一人もいませんか。」「I have no man.」と答えた彼は、なんとかわいそうな人であったでしょう!
新聞に、この人に似ている女性についての記事がありました。かなり年をとっている彼女は一人で住んでいました。彼女はよく近所の方達の助けに頼りました。ある日、彼女は死にました。数日後、彼女の状態を調べに行った人は彼女の死体を見つけました。警察が調べに来たとき、彼らは彼女の日記を見つけました。その日記の終わりのほうに同じ言葉がすべてのページに書いてありました。
「Today no one came.」 (今日だれも来なかった。) ヨハネの5章の男性の言葉「I have no man.」と新聞の記事の女性の言葉「Today no one came.」が日本とほかの国々にいる多くの人々の状態を表していると思いませんか。
彼らの街に伝道に熱心な教会がありませんから、彼らの魂に関心を持つ人がいません。昨日だれも彼らの町に福音を述べ伝えに来ませんでした。今日もだれも彼らの町に福音を述べ伝えに来ません。明日もだれも彼らの町に福音を述べ伝えに来ません。
キリストがこんな人たちを見たとき、彼は「彼らをかわいそうに思われた。」(マタイ9:36)英語の聖書は「compassion」という言葉を使っています。英和辞書によると、「compassion」は哀れみと同情です。
しかし、「compassion」の本当の意味はもっと深い意味です。人たちの状態を見て、彼らをかわいそうに思うことと彼らを助けてあげたい気持ちを持つことです。
私たちはよく宣教師たちの経済的な必要を強調しますが、もし私たちが「I have no man.」と嘆いているたましいの声を心で聞いたら、私たちは彼らをかわいそうに思って、彼らを助けるためにできるだけのことをするでしょう。海外宣教の最も大切な必要は「money」 ではなくて、「compassion」です。問題は、私たちの財布にお金がありますかという事ではありません。私たちの心に「compassion」がありますかという問題です。なぜなら、私たちが福音を伝える宣教師がいない町に住んでいる数多くの魂をかわいそうに思って、彼らを助けたい心を持つようになるとき、私たちは喜んで財布を開けて、海外宣教のための献金を捧げるからです。
小さな教会の宣教
枚方聖書バプテスト教会牧師 當麻 眞平
アンテオケの教会のように
「そこで一同は、断食と祈りをして、手をふたりの上においた後、出発させた」(使徒13:3)。アンテオケの教会は、聖霊の導きでサウロを宣教に送り出しましたが、その時のアンテオケの教会はどのような状態だったでしょうか。宣教を始めるにふさわしい、十分に成長していた教会だったのでしょうか。アンテオケの教会は、ステパノのことで起った迫害のために散らされた人々が伝道して始まった教会です(参照、使徒11:19−21)。まだまだ始まったばかりの教会ではなかったでしょうか、しかし彼らはパウロ達を宣教に送り出しました。
枚方で開拓伝道を始めてから、もうすぐ40年になります。小さな教会です。会堂は与えられていますが、土地の取得や建物の建築のために多額の費用がかかり、経済的に苦しい時代が長く続きました。今まで教会を継続することができたのは、主の守りと祝福があったこと、そしてしっかりした目標を持っていたからと信じています。それは世界宣教に参加することです。枚方の教会は、母教会から送り出され、多くの姉妹教会に支えられて開拓が始まりました。人々が集まり、救われる人も起こされ、教会としての形が見えてきました。
アンテオケの教会はどうだったでしょうか。アンテオケにまで進んできた「散らされた人々」は主イエスを宣べ伝えました。「そして、主のみ手が彼らと共にあったため、信じて主に帰依するものの数が多かった」(使徒1:19−21)とあるように、アンテオケに教会が出来たのです。しばらくしてアンテオケの教会は、聖霊に導かれてパウロとバルナバを宣教に送り出しました。アンテオケの教会と同様に、私たちも、パウロとバルナバはいませんが、信仰約束宣教献金と祈りをもって参加することに決め、すぐに開始しました。
開拓伝道開始と同時に世界宣教に参加
枚方教会は、開拓を始めてすぐに世界宣教の働きに参加しました。その時教会は、母教会や姉妹教会から祈りと献金の支援を受けている最中でしたが、「宣教の大命令」を実行しない教会はあり得ないと思っていました。「それゆえに、あなたがたは行って、すべての国民を弟子として・・・」(使徒28:19)。これは第一に世界宣教をせよと示すものと考えます。もちろん、開拓伝道ですから、足元の伝道が最優先です。地元の伝道をせずして信徒を得ることは出来ません。この足元の伝道は、当然行うものであって、必然的に行います。では、世界宣教はいつ始めるのが最善でしょうか。教会が成長して自立し、教会員も十分に確保できた時が世界宣教を始める時でしょうか。私は、開拓伝道を始めた時こそが、世界宣教を始める時であると信じています。教会が成長してから始めようとしても、かえって色々な必要や問題が教会内にあって、外に出て行く教会の力である世界宣教は、しづらくなるのではないでしょうか。しかし、開拓期から始めているなら、世界宣教は教会の働きの一つとして定着するので、教会が経済的に苦しくなっても、何か問題が起こっても、世界宣教に捧げることは当然のこととして継続が可能です。それは足元の伝道をやり続けるのと同じことです。
教会と世界宣教
私は、この小さな教会が今も維持できているのは、礼拝を行い、伝道を続け、同時に世界宣教に参加しているからと信じています。つまり、主の宣教の大命令を守ってきたことで、教会は主の恵みをうけて守られているのです。私たちは教会の成長を願う時、私たちの思いは内側に向かいがちです。設備のため、伝道のために力もお金も必要ですから、外に出すことは無駄遣いに思えます。海外宣教は大切ですが、教会が第一でしょうとなるのです。しかし、主の命令は、第一に「あなたがたは行って」宣教することです。教会の成長のために、外に向かうことは決して損失ではなく、海外宣教は教会の力の源泉となるものです。流れ出ますが、枯れることはありません。宣教は、教会の力であり守りであると思います。教会はつねに一致して守られます。宣教をやめて、その力を教会のために使うなら当座は繁栄があるかもしれません。しかし、教会の基礎は緩み、亀裂もおこり、いつしか教会は傾いてしまうことでしょう。宣教は、教会の霊的な恵みです。
信徒と世界宣教
普通の教会の普通の信徒の働きは、世界宣教にどれほど貢献しているでしょうか。使徒行伝には、多くの聖徒の働きが記されています。使徒たちの働きは特に興味深いものです。その中でもパウロの働きはとくに素晴らしいものです。海外宣教をしている宣教師の働きには、心躍らせるものがあります。普通の信徒の働きと比べることは出来ません。しかし、使徒行伝において、最も注目しなければならない宣教師たちがいますが、ほとんど注目されません。彼らは、実際は使徒でも伝道者ではなく、普通の信徒たちです。
ステパノが殉教し天に召された後、「エルサレムの教会に対して大迫害が起り、使徒以外の者はことごとく、ユダヤとサマリヤとの地方に散らされて行った」(使徒8:1)のです。「さて、散らされて行った人たちは、御言を宣べ伝えながら、めぐり歩いた」のです。その中にいたピリポはサマリヤに下っていき、人々にキリストを宣べはじめると、彼らはピリポの話に耳を傾けます。その結果、サマリヤの人々は神の言を受け入れたのです。そしてエルサレムにいる使徒たちは、ペテロとヨハネをそこに遣わして、主イエスを信じた人々にバプテスマを施したのです。これらの名もなき信徒たちは、エルサレムを追い出された人々ですが、福音を町々に宣べ伝えた宣教師です。彼らの働きが各地の教会の基礎となったのです。
一人の信徒の働きは、ある意味でわずかな献金と祈りであるかもしれませんが、その働きの一つ一つが集って世界宣教を動かすのではないでしょうか。その一つ一つは、目立たなくても、なくてはならない働きなのです。宣教の地を訪問し伝道を助けることもなく、ただ宣教報告を聞いて、祈るだけかもしれませんが、その小さな働きがなければ、大きな世界宣教の働きは始まらず、また継続できないのです。世界宣教は本当に大切です。宣教師の先生方の犠牲に心から感謝します。そして、その働きを支えている信徒の働きにも心から感謝します。続けて世界宣教のために祈り、またささげましょう。
異邦人・異民族伝道と教会
〜文化の違いを超えて出て行くときに気づかされたこと〜
インドネシア派遣宣教師 広瀬 憲夫

「また、こうも言われています。『異邦人よ。主の民とともに喜べ。』さらにまた、『すべての異邦人よ。主をほめよ。もろもろの国民よ。主をたたえよ。』ローマ15章10〜11節
異民族との向き合い方
世界中の「難民」問題で関係者はそれぞれに難しい対応を迫られています。私たちの近隣にもミャンマーからロヒンギャ族難民が押し寄せてきていて、いくつかの難民キャンプが作られているそうです。
難民到着後、この9月、スタバッ伝道所の近くのモスクから、拡声器を通して周辺住民にも聞こえるように伝えられた説教が、「帰って闘え!」でした。この説教者の個人的な見解でしょうが、今の時代、違う民族、違う文化、違う宗教の人々の間の対立が、ますます深くなってきていることが肌で感じられる言葉です。
そのような状況の中で、私たちは異民族に対してどうするようにと主から命令を受けているのでしょうか。
旧約聖書において、「主の民」(ローマ15:10)とは割礼を受けてアブラハム契約に入った者であり、「異邦人」は、それ以外の割礼を受けていないすべての人々を指しています。パウロの手紙ではそれを受けて、「すべての異邦人」「もろもろの国民」も福音によって主をほめるようになることをビジョンとしているのです。
使徒時代のローマ帝国同様、インドネシアも多民族国家です。インドネシアで隣人は、共通語としてインドネシア語を話すことができても、多くの場合、日常ではそれぞれの民族語で会話をする、さまざまな民族です。その数はインドネシア全体で、300以上とも700以上とも言われます。インドネシアにおいて、隣人への伝道は、本来なら異民族への伝道のはずです。
民族の違いによる障壁
ここで障壁になるのが、その民族の違いでした。北スマトラ州では、一般に「キリスト教=バタック民族宗教」と思われるほどに、バタック民族教会が多く存在します。バタック・トバ族の場合、国勢調査の統計上、95パーセントがキリスト教。そして、私たちの教会でも、メンバーの9割はバタック族です。そのため日常の交流も伝道の相手も、バタック族が多くなります。バタック民族教会はプロテスタントを標榜しているにもかかわらず、救いは善行によるとする教理なので、彼らへの伝道は「信じるだけで救われる」というところに力が入ってしまいます。
実は、宣教地に来た最初のうちは彼らが何をどのように信じているかに、あまり注意を払っていませんでした。イエス・キリストを信じると言うのは、私たちにとってはなによりもまず贖いを個人的に受け入れ信じることです。それに対し、「彼らは贖い信仰50%プラス善行50%としていて、信じるだけでは救われないと考えている」と私たちは考えていたのです。
けれども、「信じた、救われた」はずの人々のその後の成長がどうもはっきりしない。そのうちに少しわかってきたのが、彼らの言う「キリストを信じた」とは、数ある宗教の中からキリスト教を選んだことであり、数ある神々の中からキリストを選んだ、生まれながらの家の宗教がキリスト教だった、ということにすぎなかったわけです。バタック民族教会で十戒や使徒信条を毎週のように唱和してもキリストの死が「自分のため」という自覚はなかったのです。
贖いの理解が不十分なままに「イエスは主である」と信じて告白し(させ)ても、信仰生活はせいぜい律法主義にしかなりません。加えて、年長者を尊重することが何よりも重要とされる部族社会の伝統の中で、年長者の権威に強制力を持たせる権威付けのための聖書の教えにとどまってしまいがちです。ですから、そのような状態の人々に、「信じるだけで救われる」という点だけを強調して伝えても、実は、空を打つような拳闘をしていたに過ぎなかったと言えます。
他宗教の異民族に福音を伝える際には、もちろん、「信じるだけで救われる」というところだけを強調するような「伝道」はしません。そこは、自分でも無意識に、相手によって伝え方を変えていたわけです。
特定の民族文化が教会の習慣となってしまう
教会メンバーが「隣人」に証しをするにも、バタック人への伝道がどうしても多くなり、「異民族」、すなわち他民族、他宗教の人々への伝道は二の次になってしまいがちになります。さらに、教会内のさまざまな行事、話し合いのやり方、等々、気づかぬままにバタック民族文化が濃厚になってしまいます。教会内の雰囲気が、多数派であるバタック民族の色になるのは、仕方ないことかもしれません。けれども、まさにこのことが「異民族」伝道の障壁になっているように考えられるのです。
地域に根ざす教会として地域での証しに励むとき、周辺の人々を区別することはあってはなりません。しかも、宣教の大命令は、「すべての国民」を目指すように明記されているのです。そこで、私たちは教会のあり方の原点、教会の宣教の原点を考える必要があると気づかされました。教会の宣教原理の第一歩を、同胞に向けるのか異民族に向けるのか、ということです。「出て行って、すべての国民を弟子とし」との命令を聞くとき、どこに目標を置くべきでしょうか。どのような教会を目指していくべきでしょうか。
教会本来のあるべき姿を取り戻すには
バタック民族が多数になってしまっている私たちの教会の状況の中に自分を置いている時、このことには気がつきませんでした。いつも付き合っている人たちが、御言葉を語る対象になり、その友人、家族がおもな伝道の対象となる。
そこをあえて、自覚的に異邦人、異民族と接触し、伝道することに心を向けることから、他者の理解を深める機会も与えられてくることになり、さらには、教会でなされるべき教え、特に青年に対する指導が、異民族どうしの集まりとして学ぶべき聖書の教えを追及することから始まることになるのではないでしょうか。
このように、異邦人・異民族伝道が、必然的に、教会本来のあるべき姿、本質を明らかにしてくれるように思われるのです。
教会の本質に触れる話し合いへの招き
今年の6月、東アジア宣教師O師にビンジェイに来ていただいた折、教役者の交流の必要性を強く感じ、雑談の中から、「各国の伝道者が集まって交流会を開こう」、という計画が持ち上がりました。互いの宣教地のために祈りあい、理解しあい、さらにはやがて宣教師を送り出すための力を得るための交わりを目的とする集いです。東アジア内地から、何名かの若い伝道者が、メダンに来ることが可能かもしれません。それに合わせて、日本の伝道者の皆さんにも、ぜひ、積極的に、この交わりに参加していただきたいと思います。東アジアの参加者と忌憚なく語り合うためにも、特に若い伝道者の皆さんにお願いしたいと思います。期日は、2018年5月14日(月)から18日(金)まで。場所はメダン、ビンジェイ。
ここで、教会の本質に触れる話し合いが進められ、地の果てにまで出て行き異民族の隣人となって福音を伝える教会がますます力強く成長することを、心から期待しています。
宣教の力は「復活信仰」
太田聖書バプテスト教会牧師 佐藤 一彦

「キリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなたがたの信仰も実質のないものになるからです。」1コリント15章12〜19節
キリスト教のイメージ 十字架
皆さん今年のイースター復活祭はいかがだったでしょうか?きっと祝福された事と思います。
最近は日本でも随分と「イースター」という言葉が浸透しつつあります(教会発信でないのが残念ですが)
しかし、どれだけの人が、それがイエス様の復活と繋がって理解されているでしょうか?
一般にキリスト教のイメージと言えば「十字架」を多くの人々が思い起こすことでしょう。確かに教会には必ずイエス様の十字架がシンボルとして飾られています。
正当な学者たちや多くの人々はイエス様が約2000年前この地球に存在していた歴史的人物であり、偉大な教師であり、奇蹟を行い、冒涜罪のために十字架で死んだことを否定していません。
そして、更に十字架の死の意味も、私たちの罪の身代わりに死んでくださり、それを信じる時に罪の重荷から解放される。この辺りまでなら、強く全否定する人はそう多くはありません。誰かが自分の命を投げ出して愛する者のために死ぬ・・・なんという美談でしょう。そのような物語や出来事は今まで歴史の中でたくさんあったことでしょう。この事実を多くの人々は信仰がなくても理解できますし、感動を与えるでしょう。しかし、それとイエス様の死とを同等に置くことは出来ません。
ある日本人宗教観アンケートで、様々な宗教の中で実はキリスト教に対する好意層が増えているという結果が出ています。結婚式はキリスト教式の教会が60%、信仰を持つとすればキリスト教が実は一番多く約30%、そしてキリスト教は好しい宗教だと答えた人が23%。このようにクリスチャンは「まじめで、信頼でき、暖かい。」と良いイメーシがあるのに、どうして未だ日本はクリスチャン人口1%の壁が破れないのでしょうか?きっとキリスト教は好ましいと思っている人々の中には、キリスト教をある種のブランドイメージで見ているのだと思います。十字架(デザインとしての形)、教会堂(素敵な外観)、愛の宗教(寛容さ)、イエス様(あるいはマリヤ様)の人物像(アイドル的存在)などが他の宗教に比べて受け入れやすいのではないでしょうか?きっとイエス様の十字架の死でさえ、最高の人間愛的な視点で見るならば好ましいのでしょう。
復活信仰がなければ信仰をもてない
しかし、私たちは知っています。それだけでは決して信仰を持つには至らないのです。イエス様の十字架に感動し、ある程度理解することは信仰が無くてもできるかもしれませんが、問題はイエス様が死んで3日目に甦ったという復活の事実を認めることだけは、信仰がなければどうしても受け入れることはできません。
なぜなら復活という真理は、人々が好む世の中の道徳、ヒューマニズムの許容範囲を遙かに超えるからです。このイエス様の復活こそ、信仰を必要とする核の部分であり、揺るぎない確信の土台となるのです。私たちの信仰は復活信仰なのです。
「そして、キリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなたがたの信仰も実質のないものになるのです。」
1コリント15章14節
パウロは15章で「イエス様の復活は事実であり、イエス様の十字架を信じた者は、すべて罪赦され、信仰によって義とされ、神の子とされます(十字架の力)。しかし、それだけではなく永遠の命が与えられ、最後にはイエス様と同じように復活の体に甦らされ、主イエス様と共に全ての祝福を得て、神の御国で永遠に生きるには復活の信仰が必要である。」と説明し、単なる地上での幸せ論ではなく、その遙か向こう側の天的な領域にまで達する祝福があることを、空想上の虚しい希望ではなく、イエス様が実際に死からの復活をもって人類に示されたのです。
しかし、パウロはこの大切な福音の真理を未信者でなく、教会に対して確認しているのです。信者でありながら、復活はあるかもしれないし、もしかしたらないかもしれないと曖昧な理解だけで終わってしまっているのであれば、それはとても惨めな人たちですと言うのです(19節)。
皆さんはどうお考えでしょうか。「復活はあれば儲けもの、無ければないでも、素敵な宗教だからいいや」と言う程度で信仰されているのでしょうか?
私はかつてウガンダの宣教師でした。現地の人々の生活は大変貧しく、物質的な豊かさを経験できる希望はほとんどありません。毎日が自給自足、或いは「無い」という生活を過ごしています。宣教師はその人々に十字架の赦しと復活という希望を伝え、多くの人々が信仰を持ちイエス様を信じ救われ、教会生活が始まります。だからといって彼らの生活水準が上がることも無く、相変わらず貧しいままです。彼らの生活を何とか少しでも助けたいと宣教師も必死になりますが、出来ることには限界があるとすぐに気づきますし、現地の彼らもそれを知っています。しかし、それでも彼らは感謝をもって教会に来て主を賛美します。なぜなら彼らは地上での生活向上に期待しているのではなく、天上の豊かさを楽しみにしているからです。彼らは復活があれば儲けもの、無くてもいいやという信仰ではなく、地上での生活(貧しい生活)が終わったら、やがて復活して天国へ行き、主にある豊かさを頂くことが必ず出来るのだという希望をもって信仰生活を過ごしているのです。
復活への期待
しかし、私たち日本では、ほぼ全ての人がある程度の生活レベルの保証があります。それに満足していないかもしれませんが、社会やシステムがそれを支援してくれますし、生活をより快適に便利にするハード面でも様々な工夫が充実しています。そのような状況の中で、復活後の天の御国にしか私の本当の幸せ、解決は無いのだという期待感をどれだけの人が抱いているでしょうか?
「イエス様に復活があった事は信じているが、私にも同じ事が起こるのかは分からないけれど、毎日神様を信じて平穏に過ごせているし、教会での交わりも素晴らしいし、いいじゃないですか!」という人の宣教には、地上での幸せな生き方を勧める宣教であって、人々の魂を揺り動かすほどの霊的宣教ではなく「私たちの宣教は実質のないものになり」(14節)得てしまいます。
私たちがイエス様の復活を信じるのは、それが「キリスト教の教えのひとつだから」だとか「もし本当なら、それは素晴らしい」と復活を客観的に見る程度のものでもなく、私たちの人生そのものに影響を与え、基盤となり、日々の生活に力を与えるものなのです。復活の事実を、遠い世界のこととしてではなく、私たちにとって意味のある、力のあるものとして生かすことが「復活の信仰」なのです。この信仰の証しを先輩のクリスチャンたちは世界に宣教してきました。それは過去の事実と現在の生活、そして将来の希望を繋ぎ合わせて人々を変える力があります。「しかし、今やキリストは、眠った者の初穂として死者の中からよみがえられました。」(20節)あなたは「復活」をあなた自身の希望としてとらえ、信仰しておられますか?それを人々に宣教していますか?